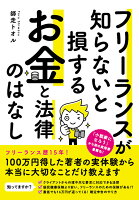この記事の解説内容
・社会人に必須の知識「社会保険」とは?
・フリーランスになったら自分で支払わなければいけない「社会保険」の種類
・退職前後にやらなければいけない社会保険の手続きとは?
無印かげひと(@kage86kagen)です!
今月も3月の末。年度が切り替わる重要な月でしたね。フリーランス1年目である私は、今月「とある手続き」が必要なため役場に行きました。しかし、そこで「もしかして損していたかも!」という出来事を体験することになります。
それがなんなのかというと、「健康保険」に関することです!
昨年の7月末に私は会社を退職し、「フリーランス」として活動を始めましたが、恥ずかしながらフリーランスになるまでは「社会保険」という制度について詳しくありませんでした。
しかし、この制度は他人事ではなく、むしろ全国民に関わる話になってきます。特に自営業やフリーランスといった方については、しっかりと把握しておいた方が良い内容です。
…ということで、今回はこれからフリーランスを目指す方向け「退職前後の手続きを忘れずに!フリーランスになる前に知っておきたい「社会保険」について」を解説していこうと思います。
- 社会保険についてそんなに詳しくない方
- これから会社を退職しフリーランスとして活動される方
上記に当てはまる方はぜひご覧ください!
もくじ
「社会保険」とは?

そもそも、「社会保険」とはどういうものなのでしょうか?ちなみに、この言葉は中学校や高校で一度は聞いたことがあるはずです…。
「社会保険」というのは、広い意味で言うと「病気やケガ、失業、出産、死亡」などに対して、お金の給付を行ってくれる「国の制度」です。
社会保険とは、私たちの生活を保障することを目的としたもので、万が一の事故に備えるための公的な保険制度です。・・・
国民がお互いに助け合う相互扶助が理念のため、多くの人が加入して母集団を作ります。その中で保険事故によるリスク分散が図られているのです。
引用元:カオナビ「社会保険とは? 基礎知識、制度の種類、雇用保険との違い、パート・アルバイトの加入条件や手続きについて」
(https://www.kaonavi.jp/dictionary/social-insurance/)
この社会保険についてもう少しわかりやすく説明すると、
「国民がお互いを助け合うために作られた制度。お互い、いつどこで何が起こるか分からないので、それに備えるためにお互い「資金」を出し合って助け合う。」
…というのが社会保険の目的です。そのため、みんながお金を出し合う必要があります。
社会保険は「5つの保険」をまとめた言葉

社会保険という言葉は、以下の5項目の保険をまとめた総称の言葉になります。
・健康保険
・年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
この5つをまとめた言葉が「社会保険」です。この5項目の中には、社会保険に疎い方でも見覚えのある言葉があるのではないでしょうか?
話が少し脱線しましたが、「社会保険」は「5つの保険をまとめた言葉」ということがお分かりいただけたと思います。
しかし、この社会保険という言葉はなかなかに厄介でして、「広い意味での社会保険」と「狭い意味での社会保険」と言うように、用途によって使い分けられています。
「広い意味での社会保険」は、先ほど説明した「5つの保険制度」のことですが、「狭い意味での社会保険」とは、
・健康保険
・年金保険
・介護保険
の3つことを指します。
今回は、フリーランスの退職前後に大きく関わってくる、この3つの意味を持つ「社会保険」の方で説明していきますね。
なんで社会保険という制度があるの?

先ほども紹介しましたが、社会保険というのは、国民がお互いを助け合うために作られた制度です。
お互いいつどこで何が起こるか分かりませんから、それに備えるためにお互い「資金」を出し合って助け合う…というのが「社会保険」の目的です。
そのため、「社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)」は、全国民が保険料を支払う義務があります。つまり強制です。
(※介護保険は、40歳以上の方から加入が義務付けられている)
「え?俺も入っているの?」、「毎月支払っている覚えが無いんだが…」と思われる方がいるかもしれませんが、「未成年(現時点で働いていない学生など)」以外は全国民が支払っています。
私も実際にそうでしたが、若い人ほど「社会保険」についての知識が疎い方も多いのではないでしょうか?
なぜかというと、会社員に属して働いている「会社員」の場合は、社会保険料は会社が勝手に手続きして支払ってくれているからです。(毎月の自分のお給料から「天引き(「控除」とも呼ぶ)」され、天引きしたお金で会社が変わりに支払いの手続きをしてくれています。)
会社に属している方は自分で支払っているわけではないので、「社会保険?なにそれ?」と認知していない方が割と多かったりします。(中には、定年退職する年配の方も詳しく知らない人がいたり…。)
退職後フリーランスになる時の「社会保険」の手続き
では、ここからは本題である「退職後フリーランスになる時の「社会保険」の手続き」の話をしていきましょう。

前の項目で話した、「会社の方で自動的に支払ってくれていた「社会保険料」」ということについてですが、…なんとなく察している方もいるかもしれません。
この「社会保険」の支払いは、退職後フリーランスに転身する方は、すべて自分で支払い手続きを行わなければなりません!
先ほどもお伝えした通り、社会保険料は全国民が支払う必要がありますので、万が一すっぽかしてしまうと…?
国から「支払いの催促」が来たり、「支払いをしていなかった間の延滞料金」がかかったり、酷い時は「財産の差し押さえ」などが行われます…!
財産の差し押さえという言葉がありますが、この場合の「財産」というのは、現金や銀行などに預けている預貯金、所有している不動産(マイホーム)などなどを指します。これが「強制的に換価(お金にされる)」されて、社会保険料の滞納金の支払いに充てられたりするんで
最悪、家や車などが持っていかれる事態になりますので、規則で決まっている以上「社会保険料」というのは、社会人は必ず払わなければなりません。
※ちなみに、金欠でどうしても支払えないなどという時は、場合によっては「免除」や「納付猶予」を申し出ることができます。詳しくは「厚生年金保険料等の猶予制度について(厚生労働省)」をご覧ください。
では、次からは「健康保険」、「年金保険」、「介護保険」の退職時の手続きについてを詳しく説明していきましょう!
退職後、各社会保険の手続きの仕方
会社員を退職する時に行わなければいけない「社会保険」の手続きは2種類あり、40歳以上の場合は1つ増えて3種類になります。順番を追って説明していきましょう。

健康保険
まずは「健康保険」から説明します。
会社に勤めている方というのは、全員「健康保険」に加入しています。会社を退職した後い、転職せずにフリーランスとして活動していくのであれば、「健康保険」から「国民健康保険(自営業者や年金生活者などが対象の保険)」に加入手続きをする必要があります。これは必ずやらなければいけません。
健康保険→国民健康保険の手続きの方法については、以下の通りになります。
- 退職前に、自分が持っている「健康保険証」を会社に返却し、会社の健康保険から抜ける手続きをする。
- 会社での手続きが終われば、「健康保険資格喪失証明書」という書類をもらえる。(超大事なので捨てないで!)
- 退職後、上記の書類を持って市町村役場に行き、「国民健康保険」の加入手続きを行う。
ざっくり説明するとこんな流れになります。役場内での手続き方法については、役場の方が丁寧に教えてくれます。
無事、国民健康保険への加入手続きが終わりますと、後日「国民健康保険の保険証」が郵送されます。これを受け取ったら、晴れて国民健康保険の加入者となります。
次に、肝心の国民健康保険料の支払い方法について説明します。
会社に所属している時は、毎月会社が代わりに支払ってくれていますが、自分で支払う場合、「毎月」の支払いではなくなります。ただ、これに関しては全員が全員同じタイミングで支払うのではなく、自分がいる自治体によって「時期」や「支払い回数」が異なってきます。
多くの自治体の場合だと、7月から翌年3月までの「10回」に分けて納めるように指示(請求書が家に届く)がきます。(ちなみに、毎月支払う金額は「1年間の社会保険料」を支払い回数分に割った金額を納めていきます。)
●[補足]会社の健康保険に加入し続けることができる!?
実はこの健康保険については、しばらくの間会社の健康保険に加入し続けることができます。これを「任意継続」といいます。
加入できる期間は規則で定まっており、最長で2年間会社の健康保険に入ったままにすることができます。
任意継続に加入するメリットとしては、人によっては「国民健康保険(略称は「国保」といいます)」料よりも「任意継続」した方が支払う健康保険料が安かったりします。(これは退職時の給与の高さによります。)
また、扶養者が多い場合は、任意継続に加入した方が国保よりも割安になる可能性があります。
この話を聞くと、「任意継続だと保険料はいくらなのか?」「国保に切り替えるとどれぐらいになるの?」と気になりますよね。
任意継続をした時の保険料は、所属している会社から教えてもらえます。国保の料金については居住している市町村役場に聞けば一発で分かります。(一応自分で計算することもできますが、かなりややこしいので役場に聞いた方が早いです。)
「なんだ、”任意継続”っていう制度があるのか。国民健康保険への手続きめんどくさいから、会社の任意継続のままでいいや!」と思った方…。この考えはもしかすると損している可能性があります!

これはまさに私が体験した出来事ですが、昨年7月末に退職した時、健康保険は「国保」にするか「任意継続」にするかの選択肢を迫られていました。
当時の私も、「手続きが面倒くさいから会社の任意継続のままでいいやー」と、国保に切り替えた場合の保険料を調べることなく、会社の任意継続に加入することを決めました。
しかし、今月の2021年3月に「任意継続を”継続するかどうか”(毎年3月に継続の確認電話が来る)」の通知を受け取った時、会社の方から「今の収入の場合、国保の方が安い可能性があるので役場に調べることを推奨します」と言われました。
安くなるなら…と重い腰を上げて役場に聞きにいったら、
このまま任意継続に加入したままだと、国保にしたときの保険料の差がどれくらいだったか?私の場合、結果は国保の方が「約1万円」安かったです!もしかすると、昨年退職した時点でも、任意継続ではなく国保の方が安かったかもしれません…。
…という苦い体験をしてしまいました。
同じように、退職→フリーランスになる方は、面倒くさくても役場に国保の値段を聞くことをお勧めします。
国保の支払う額を聞く時の”聞き方”ですが、役場の方に「いついつ退職するんですけど、国保にした時おいくらになるんですか?」と聞くだけで充分に伝わりますす。役場の方に現時点での収入額を伝えることにはなりますが、これさえ伝えれば約3分ぐらいで無料で調べてくれます。
ちなみに、国民健康保険への切り替えは「退職の翌日から14日以内」と決まっています。退職したその時から役場で手続き可能ですので、国保に切り替える手続きを忘れずに行いましょう!
●健康保険のまとめ
・健康保険は、全国民支払わなければいけない。
・退職→フリーランスになる方は、2年間ほど会社の健康保険に継続して入る「任意継続保険」か、「国民健康保険」に加入するかの2択になる
・手続きは、退職前&退職後どちらとも必要。ただし、退職後に「国民健康保険」に加入する方は、退職後14日以内に手続きしないといけないので注意!
※補足
実は、「国民健康保険」に加入する以外の選択肢があります。
イラストレーターなどのクリエイター関係の仕事をしている方なら、場合によっては「国保」よりも安くなるかもしれない「文芸美術国民健康保険組合(略して「文美(ぶんび)保険」)」に加入したほうがいいかもしれませんね。
詳しい内容は以下の書籍に載っていますので、健康保険を少しでも安くしたい方はぜひとも参考にしてみてください。
国民年金保険

お次は「国民年金保険」です。いわゆる「年金」という名前で知れ渡っていますが、こちらなら健康保険よりもご存じの方は多いのではないのでしょうか?
この国民年金保険についてざっくり説明しますと、「今の高齢者を支えるために若い人がお金を支払って、将来は逆に若い人に支えてもらう」っていう、こちらもいわゆる「相互扶助」が目的の社会保険です。
この国民年金保険は、健康保険と同様に退職時に手続きが必要になります。
と、これを説明するその前に…。実は年金についても種類があるんですよ。
- 国民年金・・・20歳以上の全国民が入らなければいけない社会保険
- 厚生年金・・・会社員や公務員は、「国民年金」に加えてこちらにも加入しなければならない。
- 企業年金・・・属している会社によっては、「任意」で加入できる年金。
会社に属している場合、国民年金に上乗せして「厚生年金」というものも支払っています。実は。
…と思う方がいるかもしれませんが、その分、老後にもらえる年金が増えますので、どちらかというと会社員の方が年金の面で優遇されています。会社を退社する場合、会社員時代で支払っていた「厚生年金」は以後支払わなくなり、今後は「国民年金」のみの支払いとなります。(これもまたややこしいので、「厚生年金」についての説明は割愛します。)
そのため、フリーランスになった人は老後の年金を心配される方が大半です。
この国民年金保険の支払い方法ですが、支払い方法は多数存在します。
- 1ヶ月ごとに支払う
- 半年分、前払い
- 1年分、前払い
- 2年分、前払い
これに加えて、「現金払い」か「クレジットカードでの支払い」、「口座引き落とし」などの方法があります。意外と幅広い方法で支払うことが可能です。
現金で支払う場合は、支払い期限前に「国民年金保険料納付書」というちょっと細長い書類が自宅に届きますので、それを持って郵便局やコンビニで支払えば納税完了です。
(※割引額については、厚生労働省「令和3年度における国民年金保険料の前納額について」(PDFデータ)を参照)
さて、次に国民年金への切り替え手続きについてですが、以下のような流れで手続きを行います。
- 退職後、以下の必要な書類を持って役場に行く。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、など)
・印鑑
・退職日が分かる書類(退職証明書、退職辞令書、雇用保険受給資格書、社会保険資格喪失証明書…などのうち、どれか1つでOK。要は「退職日が分かるちゃんとした書類」を持参しなけれなばならない。) - 役場の指示に従って、役場からの書類を記入
- 提出し、OKだったら手続き完了!
国民健康保険と違い、退職前にやらなければならないことは特にありません。「退職証明書」などが手元にあれば、退職日当日から役場に直行して手続き可能です。
私の場合、退職した後自宅でスーツから私服に着替え、すぐに役場に駆け込みました(笑)

ちなみに、国民年金も「退職日14日以内」までに手続きを済ませる必要がありますので、お気をつけください。
●年金保険のまとめ
・退職→フリーランスになる方は、「国民年金保険」のみの加入となる。
・令和3年度の国民年金保険料は、16,610円 / 月
・手続きを行うための必要な書類が多いので、お忘れなく!
介護保険
最後は介護保険について説明します。こちらは40歳になると加入が義務付けられる保険ですので、39歳以下の方は読み飛ばしてもらっても構いません。
介護保険というのをわかりやすく説明すると、「40歳~64歳までの国民が強制的に払う保険料」です。
そうなんです。歳を重ねていくにつれて、もしかすると将来自分も介護される可能性が高くなるかもしれません。こちらも、「相互扶助」の心を持って支払わないといけない…といいうことです。
退職時の介護保険の切り替え手続き等は、特に何もありません。介護保険料は健康保険料と一緒に請求されますので、それだけ覚えていればOKです。
退職後、そのままの足ですぐに手続きしてしまおう!

ここまで社会保険のについてざっくり説明しました。その中でも狭義の意味である3種類の保険について説明しましたが、なんとなく分かったでしょうか?
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険(40歳以上の方のみ)
一大イベントである退職を無事終えてほっと一息つきたいところだと思いますが、上記の手続きは退職後すぐに行うことができますので、そのままの足で役場に向かうことをおススメします。
また、退職後にすぐにフリーランスとして活動したい方は、社会保険の手続きと一緒に「開業届(こちらは税務署提出)」の手続きもすると効率が良いです。開業届については、役場とはまた違った手続きになりますので、一度ネットで手続き方法を調べて見る事をおすすめします。
退職してフリーランスとなるときには、いろいろ手間のかかる手続きが待ち構えていますが、早いうちに手続きを済ませればフリーランス活動のスタートダッシュも決める事ができます。可能であればすぐに手続きを済ませてしまいましょう!
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、少し小難しい「社会保険」のお話をしました。これらはフリーランスの方は特に大事な話になってきますので、ぜひ覚えて頂きたいです。
社会保険というのは「5つの保険」の総称であって、その中でも特に、
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険(40歳以上の方のみ)
上記の3つの意味で広く使われています。
健康保険、年金保険は、どちらも退職後速やかに役場で手続きする必要がありますが、「健康保険」に関しては退職前に会社にも調整する必要があります。
これらの情報は書籍を買うまででもありません。ネット上でも無料で調べる事が可能なので、ネットで下調べするか、会社の担当者もしくは役場の方に聞くことですぐに分かります。
退職後、転職をせずにフリーランスになろうと考えている方は、社会保険の存在も把握しておいてください!
最後までご覧いただきありがとうございました!
それでは!