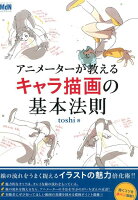この記事では、以下のことについて解説しています。
●線画が上手さに直結する話
●塗りよりも線画が難しいので、線画を優先して学ぶべき
●「ペイントソフトの変形補正」に頼らず上手くなる方法
無印かげひと(@kage86kagen)です!
イラストを描く時、「主線」と「塗り」、みなさんんはどちらに力を入れていますか?どちらもイラストを構成するために無くてはならないですが、イラストが上手くなるためにはどちらを優先的に勉強すればいいのでしょうか。
今回は、着実に上手くなりたい方向け「「塗り」よりも「線画」を極めたほうが良い理由」と、それに関連した線画練習に役立つ方法&参考書籍等を紹介したいと思います。
もくじ
線画=上手さに直結する

自分と他の人のイラスト、あるいは他の人同士のイラストの上手さを見比べてしまう行為は、おそらく誰しもが一度はやったことがあるのではないでしょうか?
絵の上手さを比べる判断材料の中で、特に線画の部分に着目する方がほとんどです。なぜなら、例え塗り方が超絶綺麗だったとしても、線の引き方が曖昧であれば「なんか、よく見たらパッとしないイラストだよね…」と、思ってしまいがちだからです。
参考に、以下のイラストを描き比べてみました。
 どちらが上手いか見比べて見ると、どちらかといえば右のイラストの方が上手に見えますね。
どちらが上手いか見比べて見ると、どちらかといえば右のイラストの方が上手に見えますね。
2つとも塗り方はまったく一緒ですが、左側の主線は人体の骨格や服のシワをガン無視して、なんとなくのニュアンスで引いているイラストになります。一見、左のイラストもパッと見は上手そうに見えますが、見慣れてくるとそうでもなくなってきますよね。
こうして見比べると、「塗り」工程も大事ではあるもののどちらかというと「線画」の方が大事に思えてくるのではないでしょうか?
塗り作業の難易度が低いのは「手法を再現しやすいから」

「線画」が重要視されるのは、イラスト業界や会社内でも同じことが言えます。
以下の引用文は参考書籍から抜粋しましたが、イラスト業界の現場でも「塗り」よりも「線画」が描ける方が重宝されているそうです。
どちらも大事だが現場で重宝されるのは線
仕事現場においてどちらが重視されるかといえば、線画がうまい人の方が重宝されます。
これは、キャラクター、背景に限らず、描ける人材が限られているからです。
(中略)
塗りは線画よりも難易度が引く(=手法を再現しやすい)ので、仕事の単価は下がります。製作ラインにおいては、まず線を量産し、それを塗りスタッフがレギュレーションにそって着色するという工程が一般的です。
塗りの表現というのはある程度手法を再現しやすいので、見様見真似でもそれなりに元のイラストに似せることができます。
これに加え、影の付け方や、オーバーレイの色合いについて、具体的な数値やカラーコードなどの塗り方の手順書みたいなものが添えられていると、その通りに色や影費の濃さを設定して塗ればいいだけですので、より原作者の描き方通りに塗ることが可能です。
しかし、「線画」というのは、トレーシングペーパーを被せて描かない限りは原作者の線に近づけることがかなり難しいです。(ペーパーでも再現は難しいですが…)原作者の主線をマネしようとしてもどうしても個人の手癖が出てしまうため、結果として主線をマネするのはかなり難しいです。
話を広げると、ここ数年ではマンガの単行本が発売される際に「モノクロ版」以外にも全ページ「カラー版」がよく発売されていますよね。
このカラー版は全部原作者が塗っている…というわけではありません。(そこまでやると原作者が疲労で倒れます!)
このカラー版は、原作者ではない別のスタッフによって着色されていることがほとんどです。そこから転じて考えると、塗りの表現というのはある程度真似ができるということです。
話をまとめると、塗り方の練習は参考文献を見ながらでも学べます。ただし、線画についてはとにかく描いて描いて描き続けないと上達できません。そのため、塗り方よりも優先的に線画に力を入れるべきだと個人的には考えています。
ちなみに、この世界には線画を完璧に真似できる超人作家さんもいますが…。
デジタルなら線画を上手く引ける「ツール」がある

線画の重要性についてお伝えしましたが、では線画はどうやって練習していけばいいのでしょうか?
簡潔に言うと、線を上手く引くためにはそれなりの練習量と期間が必要になります。手順書を見てやればその通りにできる「塗り」作業とは違い、こればっかりはすぐに上手くなれません。線画の引き方に関する参考書籍を見たり、オンライン講座などを見つつ、自力で練習していく事が大事です。
ただし、「ペイントソフト」を利用して絵を描いている方に関しては、ソフト内に備わっている「線画補正」の機能を使用すると、線画が思うように引けない方でも綺麗に引けることができます。

上記の「手ブレ補正」にチェックマークを入れるだけで、線を引いた後に自動的に補正がかかり、ガタガタの線を引いても機能の力で滑らかな主線にすることができます!
後は微調整として「アンドゥ(取り消し&やり直し)」を駆使したり、線を引いた後に「消しゴム」で線を削って微調整をする方法もあります。
ペイントソフト内の機能を利用すれば、現時点で線画がイマイチだと思う方でも綺麗な主線を引くことが可能です。
「ツール」に頼らず上手くなるための練習方法
「そうじゃなくて、ペイントソフトの機能に頼らず、自力で線画が上手く引けるようになりたい!」
…と、思っている方がほとんどだと思いますので、ここから先は、思い通りの主線を引くことができる「練習方法が載っている参考サイト」や「参考書籍」をご紹介しようと思います。
線画の練習方法は多種多様です。向き不向きの練習方法があると思いますので、下記のサイトや書籍を参考にし、自分にぴったりな練習方法を探してみてはいかがでしょうか?
参考サイト
思い通りの線を引くための線画の練習方法。
ストロークの長さがポイント
引用元:お絵かき図鑑(https://oekaki-zukan.com/articles/26628)
こちらの記事では、「線画が上手くなるためには「線の射程距離」を伸ばすこと」という点に着目し、思い通りの線の引き方について丁寧に説明されています。
確かに、線画が上手い人の特徴の一つとして線のストロークを長く引けることができることが考えられます。
ストロークの短い描き方で「シャッ、シャッ、シャッ」と「線の重ね書き方式」で描いている方の場合だと、線画の工程が長くなり、結果としてイラスト制作時間が長くりがち=イラストを描く枚数も少なくなることに繋がり、線画の上達速度も緩やかになりがちです。
そのため、線のストロークをなるべく長く引けることで、制作時間の短縮にも繋がりますし、その分枚数をこなすことが可能ですので、上達のサイクルもグングン回すことが可能です。
線画の練習の際にあまり聞くことがない「ストローク」の話ではありますが、実は結構重要な話ですのでぜひとも参考にしてみてください!
デジタル線画を克服!のびやかで魅力的な線を描くコツ

引用元:イラスト・マンガ描き方ナビ(https://www.clipstudio.net/oekaki/archives/152764)
無料お絵かき情報サイトで有名な「イラスト・マンガ描き方ナビ」でも、線画の引き方について取り上げられています。「イラスト・マンガ描き方ナビ」というサイトは、「CLIP STUDIO PAINT」を開発した株式会社セルシスが運営しています。
線画全体に関する話はもちろんのこと、各体のパーツごとの線の引き方についてのアドバイスもあります。「”目”の主線の引き方のコツが知りたい」などといったパーツごとで知りたい方は、ぜひ参考にしてください!
参考書籍
私が尊敬しているクリエイターの一人「toshi」さんの参考書籍です。この方の線の引き方は本当に参考になります。どちらかというと、「アニメ」寄りのイラスト(描き込み量が少ないイラスト)を描かれる方に適した書籍になると思われます。
また、人体のポーズもたくさん描かれていますので、「体の描き方」についても一緒に学ぶことができ一石二鳥です。
イラスト投稿雑誌で有名な「SS」からのメイキング書籍です。
こちらは「モノクロ」に重視したメイキング書籍になるので、色が絡んでこない、主線のみで攻めている作品がたくさん載っています。アナログ作品も多数ありますので、アナログで描かれる方にも参考になる一冊です。
「〇」ひとつでもいいから毎日描いていこう

どの練習方法にも言えることですが、線画は一日ですぐには上手くはなりません。日々の練習の積み重ねがあってようやく思い通りの線が引けるようになるものです。
線画が上手くなりたい方は1日1回だけでもいいので、ペンを持ってキャンパスに何か描きましょう。5分でも10分でも、内容が落書きでも構いません。言ってしまえば、ただの「◯」の連続でもOKです。
個人的な話になりますが、数年前、仕事があまりにも多忙でイラストが描けない日が続いていましたが、それでも絵を上手く描きたいがために毎日「〇」だけは描くようにしていました。
イラストの描き方は、数日描かないだけでも割と忘れてしまうものです。イラストが上手くなりたい方は自分の手に線の描き方を覚えてもらうためにも、1日の少しの時間だけでもいいのでペンを握ってなにか描いてみることが大事です。

上記のイラストは、その多忙の時期に描いたイラストです。仕事の繫忙期であっても「何か描かないと!」という思いで、毎日わずかな時間でもペンを走らせました。
分かる人には分かりますが、これは本当に重要なことです。毎日ペンと触れ合うことにより、自分の手が「絵描き専用」の手になっていきおのずと上手くなっていくような感覚になります。実際に上達にも繋がる大事なことです。
イラストは毎日の努力の積み重ねがあれば、必ず上手くなります。努力は決して裏切りません。長い努力を積み重ねることにより、必ずや自分の思い通りの線を引くことが出来るでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、「塗り」よりも「線画」を優先的に学んだほうが良い理由について紹介しました。
線画や塗りは、イラスト制作においてかかせない工程ではありますが、どちらかというと「線画」の引き方を優先して学ぶべきだと思います。
「塗り」というのはある程度マネできますが、線画はマネしようともすぐにマネすることができません。転じて、線画というのは自分の実力がもろに出る大事な部分です。
しかし、線画の上達にはどうしても多くの練習と長い期間が必要です。デジタル絵描きさんならペイントソフトの機能を利用して主線の補正を行うことができますが、作業効率の良さを考えると思い通りに線が描ける技術が欲しいところですよね。
主線の引き方についてはいろんな練習方法があります。今回紹介したサイト以外にも様々な無料講座や参考書籍が存在します。ぜひ、自分にあった練習方法を選んでみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました!
それでは!